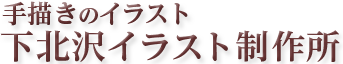「片目を失って見えてきたもの」 (2004.1.7)
44歳の時、ガンのために左目を摘出した、ピーコ(おすぎとピーコ)の本
「片目を失って見えてきたもの」より
前日の晩は、誰にも手術の話をしても泣かないと決めていたのですが、家族の顔を見るとがんばりきれず、涙が次から次へ出てきてしまうのです。もう止めようにも止められません。摘出しなければならない左目からも、涙があふれてきます。
上の姉は、ただ子どものようにすすり泣く私の背中を、やさしくさすって、こう言ってくれました。「神様、目が欲しいのなら、ひとつだけあげましょう。だから、もう、お願いです。この子からこれ以上、何もとらないで」
私はまた泣きだしてしまいました。
三歳から脊髄カリエスで体が不自由な下の姉も、「ああ、私の目を代わりにあげたい。もう、私の体には何もいらないのだから……」
と言ってくれました。
ああ、私はなんて勝手だったんだと、そのときに思いました。他人のことを思いやる気持ちが私には少し薄れていたのです。どうして、自分だけが甘えて泣いたりしているんだろう。
(がんばるのよ、ピーコ!)
私は嗚咽しながら、自分で自分を励ましつづけていました。
その頃おすぎは、毎日、忙しそうに飛びまわっていました。私の入院にどれだけの費用がかかるかわからないから、マネージャーに言って、ありとあらゆる仕事をすべて引き受け、年内いっぱい一日の休みもないくらい働く決心だったのです。
(お金のことは心配しなくていいからね。あたしが一生懸命働くから……入院してもそんなにお見舞いに行けないけど、薄情な弟だと思わないで。ごめんね。)
(中略)
ふだん、なんでもなく生活していたときはそんなこと考えもしないのに、死がとても身近なものになって、はじめて人は、自分が一人で生きてきたのではないことに気づくものなのでしょうか。
私には、昔から友達と呼べる人がたくさんいました。でも、それも当たり前のようで、特に意識していませんでした。それが、ガンになってはじめて、「自分のことを考えてくれている人がこんなにたくさんいるんだ」ということを知り、びっくりしました。
そんな人たちの存在が、ありがたくてありがたくて胸がいっぱいになりました。
「なんて私は幸せなんだろう」
ガンにならなければ、その人たちのありがたみに気づかなかったなんて、私はなんてばかだったんでしょう。
永六輔さんに言われた言葉は、一生忘れられません。いまでも思い出すと、目頭が熱くなってきます。
「僕は、きみとおすぎを『縦糸』の友達にしたからね……」
「え、どういうこと?」
「織物は縦糸が決まらないと、横糸がひっかからない。つまり、縦糸は一生の友、横糸は一過性の友ということだよ。これはきみたちの問題じゃないんだ。僕が勝手に決めたことだから。きみが何をしようと、きみがどんな意地悪な口を叩こうと、僕は絶対にきみたちに怒らない。だって、きみたちは縦糸の友達なんだもの」
たしかに、永さんの言うとおりかもしれません。本当の友達とは、そういう関係でなければならないのだと思います。
ハリウッド映画 (2004.1.9)
久々にハリウッドの映画を観ました。映画自体が久々でした。いま話題の「ラスト・サムライ」で、確かにおもしろかったし、なかなか日本をよく描いていたとは思う。もちろん、細かいあれこれに「おいおい;;」はあったけど、いままでに比べたら変な誤解は少なかったし、エンターテイメントに仕上げるためもあったでしょう。
1ヶ月ほど前だったか、この映画について、アメリカ人コラムニストの評が日本の新聞に出ていた。良くできたエンターテイメントだが「ハリウッドの悪い癖。なんで全部説明しちゃうかねえ。観客が想像する自由を奪っている。」と書かれていた。
で、実際に観てみて、たしかに・・・、そこまで描かなくても、という印象は強い。もちろん、このコラムを読んでいたので、その部分を気にして観ていたという先入観はあったはず。2時間半という長い映画だったけど、その長さを感じさせない内容ではあった。でも、日本人が日本人の感覚で作ったら、最後の1時間はカットするんじゃないか?と思われた。
もちろん、これから観る人もいるだろうから、内容については書けないけど。最後の方では、「この前」でエンディングにしてた方が良かったんじゃないの?と思いながら観ていた。
確かに感動するようなエンディングには仕上げてある。決して悪い出来ではないと思う。でも、ハッピーエンドだったのかそうでなかったのか、結局どうなったんだ?というのを白黒させないと気が済まないのかなぁ?という感じだった。まぁ、どうなったんだ?と思わせておいて、続々と続編を作る常套手段がお得意ではあるけど。
以前、日本映画とハリウッド映画の違いについて読んだことがある。日本の場合、みんなほとんど価値観が似ているので、ある程度まで表現すれば、「この先は言わなくてもわかるでしょう」という部分が多い。それに比べて、欧米は「言わなきゃ、相手には絶対にわかるわけがない」。だから、徹底的に描く。ハリウッドなどが誰にでも簡単に受け入れられる背景は、その部分が大きいと。
でも、そういうのと、想像して楽しむ部分を残すというのは全然違うと思うのだ。「ラスト・サムライ」は、そういう意味で描きすぎだとは思う。でも、観る価値は大いにあるでしょう。アメリカ人にウケる映画か、と考えると、??だけど。あちらの映画にしては、珍しく日本が変に屈折して描かれていなかったとも思うし。
秒速 (2004.1.11)
昨年初冬の頃、連日強風が吹き荒れた。
ニュースでは、瞬間最大風速40mを記録したところもあると言っていた。ほとんど台風である。
友人とその話になったとき、友人は言った。
「風速40mって、、時速?」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほとんど、ストップモーションぢゃん;;;。
いちびりのカガミ (2004.1.15)
あちこちに書いたけど、卒業してコンピューター関係の会社に就職して、最初に配属されたのは大阪支店だった。オンラインシステム開発の仕事で、主に神戸の灘神戸生協のシステム開発に携わっていた。
生協のコンピューターを扱うので、自分の会社へは行かずに、現地に直行直帰の日々だったりした。なので、結構正式な時間より遅く出勤したり、決められた時間より長い昼休みをとったりしていた。チームの責任者(課長クラス)も一緒なので、大手を振ってである。それでいて、連日深夜までの残業だったりしたのだけど…。
現地では、毎日のようにお昼を食べに行く店が何軒かあり、最後にくつろぐ喫茶店も決まっていた。ある割烹の店のランチもよく食べに行っていた。ご主人ともなじんでいて、ランチにちょっとサービスをしてくれたりもした。
ある日、ランチを頼もうとお店に入ると、ご主人がニコニコしている。
「は~い、はい。みんな、二階にあがって~♪」と、満員の時に使う2階の座敷に通された。
そこには二グループに分けた「鍋」が用意されていた。だいたいいつも、6~8人くらいで食べに行っていたので、その人数がまかなえる鍋料理である。もちろんランチとは全く違う。ご主人が我々のために、食べに来る時間にあわせて、鍋を煮て用意していたのだ。料金はもちろん、通常のランチ料金。料理内容はそれを超えていたが。
一同「お~~」とは思ったモノの、「???」である。なにしろ、予約をしていたわけではない。ほかの店に食べに行っていたかもしれないし、そもそもその日にその地に来るという保証だってないのだ。
「オレら来ぇへんかったら、どないすんねん?」である。女将さんも「ホンマにこの人いちびりやから、来るかどうかわかれへんのにやめとき言うたのに、うれしそうに用意して…」
もしや、その店に行かなかった前日も、用意していたのか?もしそうであっても、マイナスには考えずに、来る日まで同じ事をやっていたのではないか?何となく自分を見ているような気がした^^;;;。
「お忙しいところ…」 (2004.1.17)
「ご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。この電車、終点新宿へ2分遅れましての到着となります。お急ぎのところ申し訳ございません。」
先日、電車に乗っていたときのアナウンスである。この2分が1分の遅れでも、同じようにアナウンスされるでしょう。たかが1分や2分で。まぁ、割合乗車の少ない暇な時間帯とは言え、確かに急いでいる人もいるとは思う。でもなんかいつも釈然としない。
仕事がらみの電話でも、「お忙しいところ誠にすみません。」というのは常套文句。おもしろいことに、メールでも「ご多忙の中、申し訳ありませんが…」というのが普通だったりする。季節や時期に無関係に、同じ調子である。
忙しいことがいいことで、相手がそのいい状態であるという外交辞令もあるんでしょう。でも、こちらはそのとき、暇なときだってあるわけで、そういうときは「いや、暇ですけど」と思わず訂正を入れたくなってしまう。特に、暇なときに「大変お忙しいのに・・・」なんて言われるとよけいに。
ただの挨拶のフレーズだということはわかっているが、なんかいつも忙しくしていないといけないのか?という反発も感じてしまうので。
誰も、忙しい状態が本当の幸せな状態である、なんて思ってはいないと思う。忙しい=「ありがたいことに仕事があって、暇がない」であり、生活するためにはいいこと、になっているのは、しょうがないことではあるけど。
同じく納得がいかないのは、同じ分量の仕事をこなしても、いっぱいいっぱいでやっていて、忙しそうに見える人の方より、非常に要領がよくて暇な時間を作れる人の方を、非難するような雰囲気の事が希にある、と言うことですね。
器用貧乏? (2004.1.19)
やり始めると凝ってしまう。それで、まぁほどほどには、たいていのことは器用にはこなせるところはある。でも、器用貧乏ではないか?とも思っている。
そんなことを言っていたら友人が言った。
「い~じゃん。オレなんか不器用貧乏だもん」
薄暮の風景 (2004.1.21)
 夕暮れの風景は人並みに好きなんですが、どちらかというと夕焼けになる前の薄暮の状態が好きなんです。こんな感じ →
夕暮れの風景は人並みに好きなんですが、どちらかというと夕焼けになる前の薄暮の状態が好きなんです。こんな感じ →
鮮やかな夕焼けはそれはそれできれいでいい。でもその前の、中途半端な絵にもなりにくいような状態が何とも言えずいい。
なんて言うのか、「心の琴線」とまで言ってしまっては綺麗に言葉にくるみすぎだし、昼間の喧噪や仕事にいそしんでいた町の空気が、ため息をついて、「今日も一日が終わるにゃぁ」という、時間が一瞬止まったような空気を感じる。車の運転で言うと、色彩がもっともわかりにくい状態の時で、信号の色を見誤ることもある危険な時間帯でもある。
 家の近くに小田急線の踏切がある。西日が沈んでいく方向が、線路の下り方向になり、そこで見る薄暮の夕空がとても郷愁をそそる。自分の記憶の心象風景と言うより、多くの人の共通の心象風景という方がしっくりくる。
家の近くに小田急線の踏切がある。西日が沈んでいく方向が、線路の下り方向になり、そこで見る薄暮の夕空がとても郷愁をそそる。自分の記憶の心象風景と言うより、多くの人の共通の心象風景という方がしっくりくる。
あえて言えば、一日が無事に終わろうとしている、という感覚に近い。人が夕焼け対して、ことさらに特別な感傷を抱くのは、古代から、さらに言えば人間の進化の途上で、一日を無事に生き延びた、という証として、刷り込まれてきたモノなのかな?なんて事も感じたりもした。
つきあいが悪い (2004.1.24)
「つきあいが悪い」という非難の仕方は、日本人独特のモノなのだと思うけど、どうなのだろう?学生時代なら、みんなで何かをやるときや、コンパなどで飲みに行くときに、それにつきあわないと「お前、つきあいわりぃな」と言われたりすることがあった。
社会へ出ても、そう言うことはよく聞くが、幸い自分が居た所ではそういう事はなかった。みんなで飲みに行くのも、遊ぶのも、楽しむためなのだから、気が乗らないとか、都合が悪いのは仕方ないのであって、また行けるときには行こう、という感じだった。
社内で飲みに行って、帰りたくなったり早く帰らなければいけないときは、心おきなく帰った。馬鹿な上司に、早く席を立つことを詫びなければならない、と言うことなどはなかった。そういう点ではみんな大人だったというか、当たり前というか。
考えたら、なんで「つきあいが悪い」なんて言われなければいけないのか?いつもつるんで行動している人たちが、いつもいつも積極的な気持ちなのか?というと、そうでもないらしい。毎回のようにみんなで飲みに行っている人たちの一人は、「一回でも抜けるのが不安」なのだと言った。
必ずいつも行動をともにすることで、友人仲間である、というつながりを保っていないと不安なのだそうだ。本人がそう思っているだけなのか、本当にそう言う雰囲気を漂わせているグループなのかは、判断の難しいところ。ちなみに、その人たちは若いけど学生ではなく、バイトで働いている人たちだった。
中高年でも、そういう「つきあいが悪い」という言い方をする人はいる。はっきり言って、そう言う人は精神的に自立していない人なのだろうと勝手に思っている。自立していなくて他人への依存心が強いから、仲間だと思っている人が、自分と行動をともにしないことに不満というか、不安を覚えるのだろうと。チームワークを大事にする、という事とは、明らかに次元の違う話であるし。
自分は明らかに「つきあいが悪い」方の人種である。あまり大勢でつるんで行動することを好まない。そういうことに対して、非難めいた気持ちをもっているのではなく、単に人間のタイプの問題である。もちろん、クラス会であるとか、ある種の集まりならば、大勢が集った方が楽しい。でも、普段のつきあいならば、なるべく話が全員に届く範囲の少人数がいい。いい意味で、個人の行動を尊重する傾向も、近年は出ているんではないかとも思うが…。
やり直せるなら… (2004.1.25)
ちょっと古い歌だと、ユーミンの「あの日に帰りたい」なんてのがありましたが、「あの頃に戻れたら…」なんてのは、誰でも考えた経験のあることなのでしょうね。もちろん、自分もそんなことを思った記憶はある。
元々は、すんだことをグジグジと考えて、後悔することもしばしばの性格だったけど、就職して大阪に住むようになった頃には、そういうのもなくなっていた。
それでも、「あれをも一回やり直せたら」と言うことはまぁ、時にはある。でも、それはあくまで、せいぜい何日か前のことだったり、今やっていることに絡んでの事だったりする。これは歌にあるように、○○の頃に帰りたい、ということではない。
よく、子供の頃に帰りたい、というのも聞く。あれ、どんなだろう?と考えたことがあるのだけど、よく考えたらとんでもないと思ったのだった。
たとえば、小学校の頃に戻りたい、と思うとすると、そのころの状態に戻って、もう一回子供の頃の楽しさを味わいたい、という事だったりするのでしょう。でも、それには、今の自分の状態の記憶を持って行く必要がある。完全にそのころに戻ってしまうのでは、何の意味もないでしょう。それでは、戻って楽しみを味わうことはできない。今の記憶と精神状態を持って、その頃に戻りたいと言うことでなければ矛盾してしまう。とすると、今のあらゆる経験や記憶も持って、その子供の状態に帰り、そこからまた人生をやり直すわけだ。そんなことが耐えられるか?と思い当たってしまったのだった。
まぁ普通は、ただいっとき、その頃に戻ってみたいというだけなのだろうけど、もし、再びすぐに大人に戻ってこれないのだとしたら、それでも帰りたいと望む人はいるのだろうか?
テクニック (2004.1.27)
作家・保坂和志さんの「書きあぐねている人のための小説入門」を読んだ。いや、別に小説を書こうと思っているわけではないのだけど、現役作家による小説の書き方の本はきわめて珍しいので、どんな内容かと気を引かれたのです。
たいていは、自分ではまともな小説なんぞを書いたこともない、編集者や評論家による、形式ばかりの「小説の書き方入門」みたいなモノしかないと、この本にも書かれていた。失礼ながら、この保坂さんの小説は読んだことはない^^;。
さて、この本の感想や論評をするつもりなのではない。興味があったら読んでみてください、というところです。だけども、どうしてもひとこと言いたい部分があったのだ。この本の中に、次のようなくだりがあった。
絵の展覧会に行くと、最前列にいて細かく絵を観察している人がいるけれど、彼らはたいてい美大生だ。彼らも絵のテクニックばかり見ていて、本当の絵の絵たる部分を見ていない。テクニックというのは語りやすいものなので、テクニックを知るとそこだけを見てわかった気になってしまう。それが技術論(=形あるもの)の弊害で、「考える」ことをそこで止めてしまう。だから、自分が語りやすいことを考えていると思ったら、テクニックが生まれてきた元の時点=語りがたいところまでつねに立ち返るようにしなければならない。
これは、著者の勘違いと知ったかぶりによる文章だと思ったのだ。本全体はとてもおもしろく有意義だった。ちょっと独りよがりな部分も多く感じられたけど、考え方などがとても参考になった。
でも、上記の絵に関する部分は、ちょっと違うと言いたかった。おそらく著者は、絵は全く描かないか、もしくは描いても、結局テクニックにとらわれてしまいがちになるんではないだろうか。
以前は自分も、他人の絵を細かく観察している人は、テクニックにとらわれていると思っていたのだ。もちろんテクニックにとらわれて、そのように観察している人は多いと思う。
でもやがて、そればかりではないことがよくわかったのだ。絵からやや離れて(距離をとって)観る見方が正しい、と決めつける評者がいる。細部を観るのは、細かいテクニックにとらわれたり、木を見て森を見ていないことであって、絵そのものを観ていないと。
でも、細かいところにも作者の思い入れはある。そして、部分部分の筆跡やそう言う細かいところに、作者の制作過程を感じる事だってあるのだ。保坂氏は、「本当の絵の絵たる部分を見ていない」と決めつけているが、それは彼自身の決めつけでしかない。
まぁ、そのことは自覚していて、あくまで自分自身の考えを書いたのであって、読者は読者で判断してくれ、ということなのかもしれない。おそらくその可能性は強い。でも、それでも敢えてこの点に関しては書いておきたかった。
この本の中では繰り返し、小説はテクニックで書くものではない、ということが主張されている。確かにその通りだと思うけど、もしかすると著者は、「自分はテクニックを持たない」ということにコンプレックスを抱いているのか?と感じたりもした。
それにもう一つ、絵に限らず、テクニックばかりの作品というのは確かに多い。でもテクニックは、無くてもいいと言うものではないし、あればあったで作品の質を高めることもできるでしょう。なんか、テクニックに関する話になると、両極端な議論が多い気がしてならない。
テクニックがなかったために表現しきれなかったものが、そのためのテクニックを身につけることで表現できると言うことだってあるはず。自分自身もそういう経験は多い。大事なのは、テクニックというのは、表現のための道具というか、手段にすぎないということでしょう。
また、テクニックというと、水彩なら水彩のテクニックで、なんか一律なテクニックが一人歩きしているような気がするけど、本人が本人らしく表現できる「テクニック」はあっていいと思う。・・・・・・と、書いても何にも説明になってませんねえ^^;
うまく書けない・・・・。